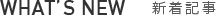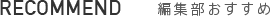2025.04.12 更新
文:エルミタージュ秋葉原編集部 池西 樹

|
統合型3Dソフトウェア「Cinema 4D」を開発しているMAXONから、2013年に提供が開始されたレンダリングベンチマークソフトウェア。「CINEMA 4D」と同じレンダリングエンジンを採用し、主にCPUの性能を検証するのに利用される。
テストは、1コアのみを使用する「シングルコア」と、CPUに内蔵されているすべてのコアを使い切る「マルチコア」に加え、グラフィックス機能を使用する「Open GL」の3種類が用意されているが、基本的にCPUに関連する「シングルコア」と「マルチコア」の2つのテストを使用する。
なお「CINEBENCH R15」は、クアッドコア世代のCPUをターゲットにしたベンチマークのため、最新のメニーコアCPUでは、クロックが安定する前にテストが完了してしまう。そのため、より高精度なベンチマークとして、「CINEBENCH R20」(後述)が2019年に公開されている。

|
統合型3Dソフトウェア「Cinema 4D」を開発しているMAXONから、2019年に提供が開始されたレンダリングベンチマークソフトウェア。「CINEBENCH R15」の後継で、より複雑なテストシーンを使用することで、レンダリングに必要な処理性能は約8倍に、必要なメモリは約4倍へと拡大。これにより、メニーコアCPUでより精度の高い比較ができるようになった。
また「CINEBENCH R15」にあった、グラフィックス機能を使用する「Open GL」が省略され、CPUにより特化したベンチマークテストに変更されている。
テストは、1コアのみを使用する「シングルコア」と、CPUに内蔵されているすべてのコアを使い切る「マルチコア」の2種類。なお「CINEBENCH R20」では、対応CPUやメモリ容量がより厳格化されており、非対応のシステムでは動作させることができなくなった。そのため、基本的には「CINEBENCH R15」と併用して使用する。

|
統合型3Dソフトウェア「Cinema 4D」を開発しているMAXONから、2020年に提供が開始されたレンダリングベンチマークソフトウェア。Appleが開発した「M1」チップにいち早く対応した他、「CINEBENCH R20」に比べて、メニーコアCPUでのベンチマーク精度が向上している。
テストは、1コアのみを使用する「シングルコア」と、CPUに内蔵されているすべてのコアを使い切る「マルチコア」の2種類で、いずれもCPUのスロットリングの影響を確認できる「10 minutes(Test Throttling)」や、安定性を確認する負荷テスト「30 minutes(Test Stability)」のオプションが用意されている。なおCPUやBTO、ノートPCの検証では、「シングルコア」と「マルチコア」の2つのテストを使用する。

|
統合型3Dソフトウェア「Cinema 4D」を開発しているMAXONから、2023年に提供が開始されたレンダリングベンチマークソフトウェア。「CINEBENCH R20」で削除されたGPUベンチマークが再実装。さらにレンダリングエンジンが標準レンダラーから、「Cinema 4D」のデフォルトエンジン「Redshift」に変更され、CPUとGPUで同じアルゴリズムを使用した、一貫性のある結果が得られるようになった。
またx86/64アーキテクチャ(Intel/AMD)のWindows/macOSに加えて、AppleシリコンのmacOSやArm(Snapdragon)のWindowsなど幅広いシステムをサポートしているのも特徴だ。
CPU向けのテストは、1コアのみを使用する「シングルコア」と、CPUに内蔵されているすべてのコアを使い切る「マルチコア」の2種類で、いずれもCPUのスロットリングの影響を確認できる「10 minutes(Test Throttling)」と、安定性を確認する負荷テスト「30 minutes(Test Stability)」のオプションが用意されている。なお基本的には「シングルコア」と「マルチコア」の2つのテストを使用し、CPUクーラーの冷却性能を確認する場合には「マルチコア」の「30 minutes(Test Stability)」を選択している。